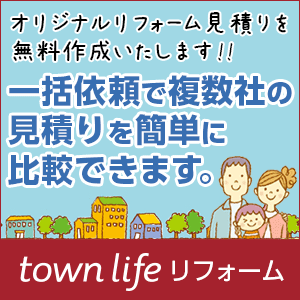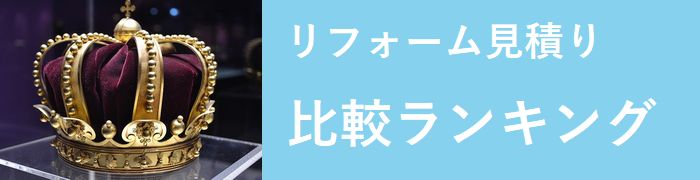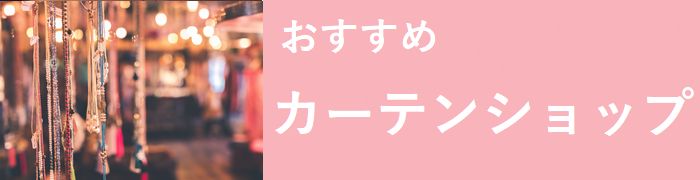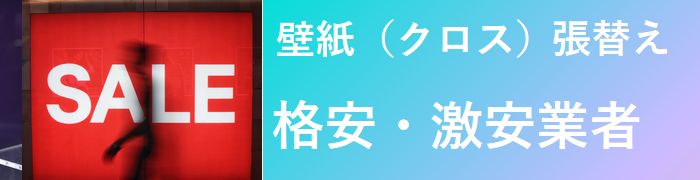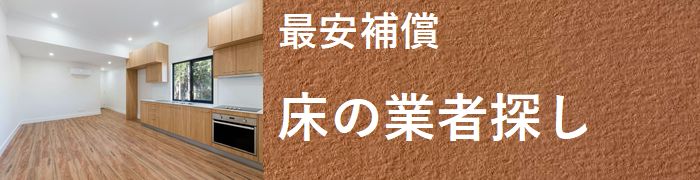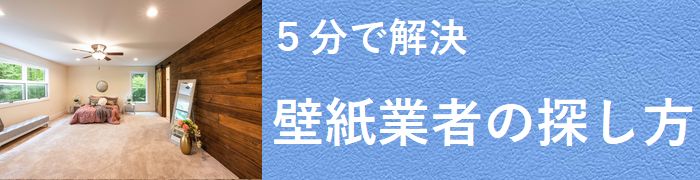親方
親方
「壁紙の隙間が目立ってきたけど職人さんが下手だったのでしょうか?」
今回はそんな疑問に答えます。
新築した住まいの壁紙に隙間ができて困ってるという方も多いのではないでしょうか。
そんな時に不安になるのが、施工した「クロス屋」さんの技術力だと思います。
「もしかしたら腕の悪い業者が施工したのかも」
なんてことを考えたりしますよね。
でも、実際のところはどうなのでしょうか?
ということで、この記事では
- 壁紙に隙間ができる理由
- 壁紙にできた隙間の対処法
- 腕の良いクロス屋さん
このような内容について説明したいと思います。
壁紙に隙間ができる理由
「壁紙の隙間が気になるな~」
という場合ですが…壁紙に出来た隙間は下記の3つのどこかではないでしょうか。
- 壁紙の繋ぎ目(ジョイント)
- 枠まわり
- お部屋の角(入隅)
多分、このいずれかに該当すると思います。
「なんで隙間が出来たの?」と思われる方が多いと思いますが、その主な理由は「縮み」によるものです。
明らかにクロス職人の腕に問題がある場合は別として、壁紙の隙間が目立つ根本的な原因には、住宅の建築材料に使われる木材の状態だったり「壁紙の収縮」が挙げられます。
なのでこれは分かっていて欲しいのですが、クロス職人の腕に関係なく、壁紙(ビニールクロス)は材質によって時間の経過とともに縮む可能性があります。
水性の糊を使って貼る壁紙は水分を含んで「伸びる」ため、温度や湿度の影響を受けたり、水分が乾燥すれば「縮む」ということになります。
この現象は「障子や襖」も同じですよね。
なので、繰り返しですが「壁紙の縮み」はクロス屋さんの「技術」とは関係ありません。
ただ、技術力でカバーできることもありますので紹介します。
壁紙で隙間が目立ちやすいところ
- 壁紙の継ぎ目(ジョイント)
- 枠まわり
- 部屋の角
先述通り、こういった場所は壁紙の隙間が目立ちやすいところです。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
壁紙の継ぎ目(ジョイント)
壁紙のジョイントはクロスを繋いだ部分になることから、最も隙間が開きやすい箇所だと言えます。
クロス屋さんの技術は100点満点だとしても「材質」や「環境」に影響されると、後から隙間ができることもあります。
隙間ができやすい壁紙の材質
隙間が開きやすい材質はというと、、「ツルッ」とした表面の壁紙ですね。
主観的な言い方ですが、壁紙の表面にボコボコした余裕がないと収縮にも影響しやすいです。
とはいえ、壁紙の「材質」による縮みはクロス屋さんの技術でカバーできますので、壁紙ジョイントの技術的なことについてはこちらの記事をどうぞ。
 壁紙(クロス)のジョイントの開きを完璧に直す方法
壁紙(クロス)のジョイントの開きを完璧に直す方法隙間ができやすい環境
また、環境でいうと「エアコン」の風が直接当たる部分は乾燥を早めるため「収縮」しやすく、隙間にもなりやすいです。
同じ時期に建てた家は問題ないのに、自宅だけに隙間ができた場合は環境も要因として考えられますが、その場合技術力ではカバーできません。
枠まわりや取り合い部分の隙間
ドアの枠や、巾木まわり、天井と壁の取り合い部分なども隙間がひらきやすいところです。
新築住宅では、築3年以内に隙間ができてしまうこともあるようですが、その主な原因は「壁紙の収縮」「木材の伸縮」この2つですね。
壁紙の収縮は施工でもカバーできますが、とくに天井と壁などの「取り合い部分の隙間」は、住宅建築に使われる天然木材の影響も大きく、建築後も「乾燥」や「収縮」が続いたり、逆に「膨張」することさえあります。
巾木まわりは「収縮」を見越して大きめにカットしておくことで防げますが、建築会社によっては、枠まわりに「コーキング」処理が必須という会社もありますので、余分にカットしない場合もあります。
少しまとめると
- 枠材まわりの壁紙は大きめにカットする
- 枠材まわりはコーキング処理する
このどちらかで壁紙の隙間対策はできますが、いずれの処理もない場合は技術力に問題があるといえるでしょう。
部屋の角の隙間
部屋の角というのは「入隅」のことです。
入隅とは、住宅の角の引っ込んだ部分のことです。
逆に、出っ張った方は「出隅」といいます。
入隅に隙間ができる原因は「入隅部分でカット」してるからなのですが、工法としては間違っていません。
入隅でカットしない場合は、建物の「揺れ」や「振動」で壁紙が膨れたり破れたりしたときに、補修が難しく綺麗に直すことができませんので、揺れを見越して「入隅」でカットし、コーキング処理するという訳です。
ただ、入隅でカットしても実際に建物が揺れると「コーキング」が切れてしまい隙間が生じる可能性はありますが、その場合上から重ねてコーキング処理をすることで簡単に直せるため、合理的な施工方法になります。
つまり職人さんの腕が悪いせいで「角」に隙間ができた訳ではなく、「揺れ」や「振動」も要因の一つということですね。
壁紙にできた隙間の対処法
それでは、実際に壁紙に隙間ができてしまったらどう対処すれば良いのでしょうか。
基本的には次のようになります。
- 保証期間内であれば業者に頼む
- 保証期間外であれば自分で直す
まず知っておきたいのは、保証期間の有無ですね。
いつまでも保証してくれる業社というのは存在しないため、自身の場合を調べる必要があります。
業者に任せた方が「壁紙が綺麗に仕上がる」のは言うまでもありませんので、保証期間内であれば迷わず連絡してみましょう。
保証期間が切れていれば「有料」になりますので、「DIY」での補修も選択肢に入ると思います。
因みにDIYをするなら、壁紙のジョイント(継ぎ目)にはプロも使用しているぺネットがおすすめです。
ぺネット
具体的には、ジョイントの隙間に「ぺネット」を流し込み、埋める使い方です。
ジョイントコークで補修する人も多いですが、ジョイントコークはいつまでもベタつき、ホコリなどで黒ずんだり、後々汚れることもあります。
その点、ぺネットは乾燥するとサラッとしますので、汚れがつきにくく綺麗に補修できると思います。
ジョイントコーク
一般的な隙間補修なら、やはりプロも愛用している水性の「ジョイントコーク」がおすすめです。
このどちらかで簡単に隙間を充填できますので、ぜひ試してください。
腕の良いクロス屋さん
壁紙の隙間について説明してきましたが、それでも自宅を施工した職人さんの「技術力」は気になるところだと思います。
ですので、クロス職人さんの技術を確認する簡単な方法を紹介します。
クロス屋さんの技術力は下地作り
結論を言うと「パテ処理」の技術です。
壁紙を綺麗に仕上げるには、平滑な下地を作ることが大前提です。
と言っても、平滑な下地作りは大工さんの仕上げにも左右されるのが正直なところですね。
はじめから凸凹した下地だと、パテ処理の範疇を超えてることも多々ありますので。
その場合、拘りがあったり上手いクロス職人は、大工さんにやり直しを求めることもありますが、必ずしもやり直しがきく現場ばかりとは言えません。
ただ「下地がいかに重要かを理解しているか」は、上手いクロス職人の見極めにもなります。
なので大工さんの仕上げは完璧なのに、お部屋の天井や壁がボコボコしていたら、そんなに上手くない職人さんだと判断しても良いかも知れません。
但し、予算等の関係で下地の交換ができず泣く泣く施工した場合は例外ですが…。
クロスの張り替えや補修をするなら
工務店や住宅メーカーにもよりますが、無料で出来る点検メンテナンス期間は最長でも「2年」が普通です。
なので、保証期間を過ぎた補修は有料となってしまいます。
金額は「5,000円~15,000円」が一般的。
内訳は「職人さんの出張費や技術料」といったところです。
それでもクロスの隙間がどうしても気になり「直したい」というなら「別の業者」も含めて考えたほうが安くなることもあります。
相見積もりを取って予算を確認する
縮んだ部分の「補修」だけではなく、張り替えも含めて「業者に依頼」するなら、相見積もりで予算を調べたり信頼できる業者を探すのは必須です。
壁紙のリフォームをしている多くの方が無料で使える「見積り一括サイト」で調査しています。
面倒な勧誘もありませんので、ご自宅の壁紙リフォーム予算を確認してみてはいかがでしょうか。
このあたりが有名でおすすめできます。
無料で使えるおすすめリフォーム一括見積サイト
専門業者に補修を依頼する
補修だけで良いという場合はリフォーム業者や工務店を探すより「クロス屋さん」にお願いした方が安いです。
壁紙の工事は「リフォーム会社」や「工務店」に頼んだとしても、実際に工事するのは「クロス屋さん」なのでクロス屋さんに直接依頼すれば中間マージンが不要です。
つまり、クロスの補修は「クロス屋さん」が最安値という訳です。
たとえば「イエコマ」では補修だけなら1か所「3,800円」でOKです。
このように実際建築した工務店より安価な方法もありますので、ぜひ活用してください。
 親方
親方
壁紙の隙間まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回は、壁紙を貼ってからすぐにできる「壁紙の隙間」について解説しました。
隙間ができやすい場所をまとめると
- 壁紙の継ぎ目(ジョイント)
- 枠まわり
- 部屋の角
このようになります。
また対処法は
- 保証期間内であれば業者に頼む
- 保証期間外であれば自分で直す
となります。
壁紙の隙間が開く原因は、クロス屋さんの技術力と思ってしまいがちですが、全てがそうでは無いということを知っていただけたら幸いです。
壁紙の寿命について書いた記事もありますので、興味のある方は参考にしてください。
 【壁紙・クロスの寿命】一般的に何年で張り替える?壁紙の耐用年数・壁紙 クロスはどのくらい長持ちするのか
【壁紙・クロスの寿命】一般的に何年で張り替える?壁紙の耐用年数・壁紙 クロスはどのくらい長持ちするのか壁紙のリフォームで失敗しない方法も記事にしています。
 【100%】クロスのリフォームが分かる!プロが教える壁紙張替え
【100%】クロスのリフォームが分かる!プロが教える壁紙張替え人気記事壁紙張り替え業者を探す方法
人気記事壁紙補修の最安値業者を探す方法